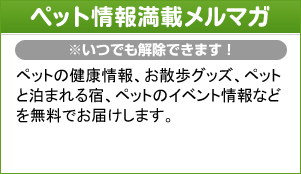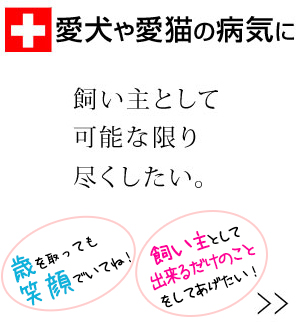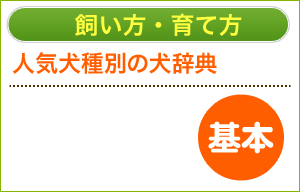- HOME
- 犬の糖尿病等ホルモン(内分泌系)の病気
犬の糖尿病等ホルモン(内分泌系)の病気
![]() 内分泌系の病気には様々ありますが、症状としては主に脱毛や多飲多尿、極度に太ったり、逆に極度に痩せたりします。
内分泌系の病気には様々ありますが、症状としては主に脱毛や多飲多尿、極度に太ったり、逆に極度に痩せたりします。
「内分泌系の病気」と聞くと何処の病気なのかわかりにくく感じますが、わかりやすく言い換えるとホルモンの分泌に問題が生じることで起こる病気です。体の中にある内分泌腺というところでホルモンが作られているのです。このホルモンが他の病気の影響を受けたり、形成的な原因により、過剰に分泌されたり減少したりと正常に働かないことにより、甲状腺や膵臓など、体の各所に影響を及ぼします。
![]() 治療は、外科手術ができる病気もありますが、ほとんどがお薬による治療になります。糖尿病のインスリン注射治療のように、どの病気も同様に、総じて長期間に渡ってお薬を与えることになります。処置を誤るとより深刻な状態に陥ってしまうため、しっかりとした検査や治療を行える病院で診断を受けましょう。
治療は、外科手術ができる病気もありますが、ほとんどがお薬による治療になります。糖尿病のインスリン注射治療のように、どの病気も同様に、総じて長期間に渡ってお薬を与えることになります。処置を誤るとより深刻な状態に陥ってしまうため、しっかりとした検査や治療を行える病院で診断を受けましょう。
| 犬の病気 症状別一覧 |
» 犬のクッシング症候群
犬のの症状と原因 犬のクッシング症候群は内分泌系疾患の1つで別名「副腎皮質機能亢進症」と言います。副腎は、腎臓の上に存在して体が正しく機能するように、さまざまな調整をするホルモンを分泌している器官です。副腎から、持続的にステロイドホルモンが過剰に分泌される症状をクッシング症候群と呼びます。ステロイドホルモンは、全身での代謝(糖や脂質、タンパク質、ミネラルなどの物質が使われること)を調節しています。犬のクッシング症候群の原因は、下垂体や副腎の腫瘍によるものがほとんどを占めます。 クッシング症になると代謝に異常が発生するため、肥満をはじめとしたさまざまな症状がおこります。クッシング症候群の症状は特徴的で、顔が満月のように丸くなる・皮膚が赤くなる・胴体が太くなる・首のつけねのあたりに脂肪がたまり、水牛のように出っぱる・血圧が高くなるなどがあります。 飼い主さんは太った事が健康の証と考える傾向も少なくなく、その他の症状を老化現象と捉える場合もあるため、病気に気づいた時にはすでに進行してしまっているという事が多々あります。放置してしまうと、免疫力の低下、糖尿病、高血圧症、心不全、行動の変化や発作などの神経症状などを引き起こし、生命の危険もあります。 犬のの治療方法・対策 医原性のものは、徐々に副腎皮質ホルモンを休薬するようになります。自然発生とわかったら、こんどは様々な検査で下垂体に異常があるのか、副腎が腫瘍化しているのかを決定します。そしてそれぞれに合った薬物療法、あるいは手術を行うことがあります。 クッシング症候群の治療には食事管理が大変重要になってきます。多飲多尿の傾向があるため、脱水症状を起こしやすいので、新鮮な水を十分に与えて下さい。また、代謝の変化により筋肉の消耗が激しくなるので、できるだけ低脂肪で適度なたんぱく質が入っているものをメインに摂らせます。基本的には獣医師さんの指示に従って食事管理をしましょう。
» 犬のアジソン病
犬のの症状と原因 クッシング症候群とは逆に、副腎皮質ホルモンの分泌が不十分なためにおこる病気です。症状は、元気がない・食欲がない・下痢・吐く・体重が減る・脱水・腹痛があります。大きなストレスを受けたあとに発病しやすく、コリーやプードルに多い病気とされています。症状が急に起きて重い症状なら危険な状況になる可能性があります。若い犬から中高年くらいまでに見られ70~80%まではメス犬になります。 副腎を摘出したために副腎皮質ホルモンが分泌されなくなったり、副腎が出血したり腫瘍ができた事により、ホルモンの分泌量が少なくなった時に表れます。またストレスを強く感じたときに発症しやすいので飼い主さんが、起きないようにケアしてあげましょう。 犬のの治療方法・対策 早急な生理食塩水(0.9%の食塩水)や副腎皮質ホルモンの静脈投与が必要です。また発生してから亡くなるまでに、副腎皮質の一種で塩類と水のバランスを調節する薬を投与するようになります。
» 犬の糖尿病
犬のの症状と原因 肝臓の細胞が傷つくことで発症するのが肝炎です。遺伝性による発症が多い慢性肝炎の場合は症状が見えづらく、元気がなくなったり、食欲がなくなる程度ですが、進行すると黄疸や腹水などが見られ、肝硬変になる事もあります。 急性肝炎は嘔吐、下痢、黄疸など。症状が進行すると痙攣を起こします。こちらは化学物質や薬剤の投与や、ウイルス・細菌・寄生虫の感染など、肝臓に負担をかけたことが原因となります。 糖分が不足すると、 食欲が異常に高まる 痩せる 多飲多尿 吐き気や嘔吐 他臓器への深刻な影響 が起こります。糖尿病は、発見が遅れ、治療が手遅れになれば、一命を奪いかねない病気なのです。 犬のの治療方法・対策 人間の場合にはインスリンを外部から補給するインスリン依存性と、外部補給の必要がないインスリン非依存性がありますが、犬の場合はほとんどがインスリン依存性のものです。インスリン注射は飼い主が生涯にわたって毎日行います。これと平行して、その対象ごとに適切な運動と食事に気を配っていきます。 初期段階で気づけた場合には食事療法と適度な運動を行って様子を見ます。場合によっては不妊手術が有効になるケースもあります。 犬のの症状と原因 食べ物などから摂取した糖分を細胞へ運ぶホルモンが、膵臓(すいぞう)から分泌されるインスリンです。このインスリンが出なくなったり、働きが弱まってしまうと、細胞は、血液内の糖分を吸収することができずに、血糖値があがりっぱなしになってしまうのです。血液内の糖分は使われぬまま、尿と一緒に排泄され、体内の細胞は深刻な糖分不足になってしまいます。これが糖尿病です。 犬のの症状と原因 糖分が不足すると、 食欲が異常に高まる 痩せる 多飲多尿 吐き気や嘔吐 他臓器への深刻な影響 が起こります。糖尿病は、発見が遅れ、治療が手遅れになれば、一命を奪いかねない病気です。 犬のの治療方法・対策 初期段階では食事療法や運動療法、また黄体ホルモンが原因の場合は、不妊手術などが有効です。また、インスリン注射を行うこともありますが、症状が改善されれば減量や中止も可能です。ただ、「インスリン依存性」に進行した場合は、生涯のインスリン注射が必要とされます。 犬の糖尿病の多くが免疫システムの異常による自己免疫疾患となり有効な予防策はありません。幼い頃から脂肪分の多い食べ物を飼い主さんが控えるなどして、すい臓への負担を減らしていれば、慢性すい炎が原因の糖尿病を防ぐ方法になります。普段から健康管理に注意して、よく食べるのにやせ始めたり、尿の量や回数が多く、水をガブ飲みするなどの症状が始まりましたら早めの対応が必要になります。 -->
» 犬の甲状腺機能低下症
犬のの症状と原因 代謝を活発にしたり、心臓・内臓・皮膚など体のあらゆる部分の活動を調整するのが、甲状腺ホルモンです。この甲状腺ホルモンの分泌量が何らかの原因で低下してしまった状態を「甲状腺機能低下症」と呼びます。この病気は猫には殆ど見られず、犬の多く見られる病気です。 甲状腺機能低下症は、甲状腺の腫瘍、萎縮、破壊などが原因と考えられています。犬のホルモンの病気では最もよく見られるもので、特にゴールデン・レトリバー、ブルドッグなどに多くみられます。発症すると、元気がなくなり、体重が増える傾向があります。基礎代謝量が低下するため、皮膚が乾いて脱毛し、寒さに弱くなり、心臓のはたらきも悪くなってしまいます。 甲状腺機能低下症は、甲状腺の腫瘍、萎縮、破壊などが原因と考えられています。犬のホルモンの病気では最もよく見られるもので、特にゴールデン・レトリバー、ブルドッグなどに多くみられます。発症すると、元気がなくなり、食欲はおちるのに体重が増える傾向があります。基礎代謝量が低下するため、皮膚が乾いて脱毛し、寒さに弱くなり、心臓のはたらきも悪くなってしまいます。この病気は、発症しても食欲の低下が見られない場合が多いため、飼い主さんは、食欲があるから少々元気がなくても大丈夫と見逃してしまいがちです。そのため放置されて病気が進行し、命を落としてしまう場合もあります。 犬のの治療方法・対策 真の甲状腺機能低下症で甲状腺ホルモンが低いのか、他の病気によりホルモンが低値を示しているのか鑑別が必要ですが、診断は甲状腺ホルモンの測定だけでは難しいため、追加の検査も行ないます。 甲状腺機能が正常であっても、老齢、飢餓、手術や麻酔処置後、糖尿病、クッシング症候群、アジソン病、腎疾患、肝疾患、ジステンパー、各種皮膚炎、全身性感染症、脊椎板疾患、免疫介在性溶血性貧血、心不全、リンパ腫などで甲状腺ホルモンが低下することがあります。他の病気が原因である時に甲状腺ホルモンの補給を行っても、病気の治療とはなりません。 追加検査で甲状腺機能低下症がほぼ間違いのないことがわかったならば甲状腺ホルモン製剤を投与して、治療への反応をみます。改善がみられているならば、次に用量の調節を行って、ホルモン補給療法を続けていきます。
※犬は生後5~7年で人間の「中年期」に入ります。 |